苗木のお城には、むかしから、白い色をきらう習慣があった。
苗木城の祖先が、戦に敗け、洞穴にかくれたとき、飼っていた白い犬が、主人を見つけて追ってきた。それを敵が見つけて、殺されてしまったという。
人々が殺し合った、遠いむかしの話である。平和な時代になると、白い犬の話は忘れられ、ただ、白い色を嫌う習慣だけが残った。
苗木の城は、木曽川の深い淵の上に立っている。木曽川の両岸は、岩山が多く、その中の、いちばん高い山にある。
山道を歩いてきた旅人は、とつぜん目の前が開らけ、青い水が豊かに流れる木曽川の岸辺に立つ。すると、空に、苗木城の赤壁をあおぎ見る。いかだ流しの人夫たちも、お城を目印にする。苗木の人々も、朝晩見るお城が、全国どこにもない赤壁であることが、何となく、ひけ目に思えた。
お城では、「白い色は、祖先からの、いいつたえもあり…。」という話もあったが、時代の流れということで、白壁にすることが決まった。
工事が始まった。村人が集められ、材木や土が集められ、馬や荷車が忙がしく動きまわる。急な坂道を、かけ声も勇ましく、運びあげる、城のまわりには足場が組まれ、みる間に、城全体が白くぬられて行く。
仕上った時には、武士たちも村人たちも、思わずよろこびの声をあげた。ちょうど、春もなかば、青葉の中に、白壁の城が、浮き上ってみえる。
「苗木にも、自慢なものが、もう一つできた。」
と、人々はよろこんだ。
すると、突然、空が暗くなった。黒雲が、北へ北へと、限りなくのぼって行く。時どき、突風が、木の枝をゆすり、ちぎれた木の葉が、小鳥のように空に舞う。
「嵐がくるぞ。」
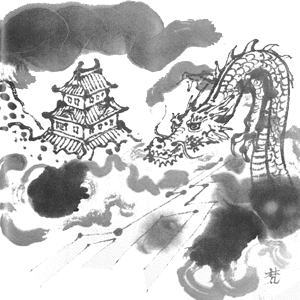 「早く家へ帰って、戸じまりをしろ。」
「早く家へ帰って、戸じまりをしろ。」
人々は、おお急ぎで家へ帰ると、嵐のすぎるのを待った。
ひと晩じゅう、嵐は、雨戸をならし、立木をゆさぶり、屋根に何かが、どかん、どかん、とぶつかる。人々は眠ることもできず、朝をまった。
夜明けとともに、嵐は去った。人々は、家のまわりや、田畑を見廻り、いたみぐあいを調べて歩いた。ふと、空を見上げると、おどろいた。
お城がない。いや、まっ白なお城がなく、もとの赤い壁の城が、みすぼらしく、折れた木の枝の間に見えるだけだ。
お城は、ほとんど、こわれた所がないのに、白壁だけが落ちている。大きな鎌でけづり取ったように、無数の傷がついていた。
ふたたび、白壁ぬりが始まった。
お城は、前よりも、いっそう白くかがやいた。
とつぜん、風が吹き始めた。南の空から、黒い雲がわき出すと、夏の雷雲のように、またたく間に空をおおった。黒雲が、地面に低くたれこめ、夜のように、あたりが暗くなった。
はげしい雨が降りだした。かみなりが、腹にひびく、どどーん、どどーん、という音を、山から山へひびかせた。
木曽川の水は、みる間に増え、城の下の淵は、大きな渦をまきはじめた。火花が、雲から雲、山から山へと、飛び廻る。ひときわ大きい火花が、渦のあたりではじけたと思うと、水柱が、渦のまん中から、天に向かって吹き上げた。水柱は、とてつもない大きな蛇のように、くねりながら、お城の天守閣を、いく重にもとりまいた。
地獄の底で、大きな歯車がきしむような音が、お城のあたりでひびきわたると、白壁が、だだだだーと、地面にたたきつけられる。
お城の中の人々が、戸のすき間からのぞいてみると、絵でしか見たことのない銀色の竜が、天守閣の屋根にあごをのせ、大きな二つの目玉を、ぐわっと見開き、こちらをにらんでいる。ひげが、空へ、のびたり、ちぢんだりしている。
するどい爪が、壁を引っかいている。白壁は、そのたびに、大きなかたまりとなり、だだだだーん、だだだだーんと、ものすごい音をたてて落ちる。
殿様は、その竜の顔が、祖先の顔に似ているように思えた。きっと、祖先の魂が、竜の姿であらわれて、白い色のいましめを、思い出させようとしているにちがいない。殿様は、祖先の、苦しかった時代のことを、忘れている今の自分のことを思った。
銀色の竜は、光とともに空にのぼり、やがて黒雲は四方に散り、青空が現われた。
人々は、しばらくは、夢をみているように、ぼんやりしてしまった。
それからは、もう白壁をぬることもなく、赤壁城と呼ばれ、苗木の人々も、それを自慢にした。
文・三宅 正幸
絵・藤原 梵
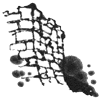
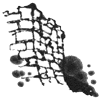
「早く家へ帰って、戸じまりをしろ。」