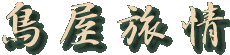
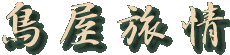
霧が動いて山の稜線が、暗闇の中からわずかに見え始めた。小鳥達の鳴声が夜明けを呼ぶ様に、その薄闇の中から湧いて来る。
寒さに思わず身を縮め、囲炉裏に小枝を投げ込む。たちまち、めらめらと赤い炎が立ち顔をほてらせる。鳥屋場での、こうして「待つ」時間と空間が、既に佳境である。
昨夜は宴席で、芸者衆の踊りを見た。長唄“賤の手振り”と“小鳥狩り”である。共に中津の酔人菅井某氏等の作との話である。こんな小さな山国に思わぬ高尚な芸能が、あまり世間に知られる事なく温存されていた事に、驚きと感動を覚えた。踊りの内容は、小鳥狩りの面白さをいかにも面白く表現しており、見る者の心を鳥屋場へといざなう雰囲気があった。
そもそも私の今回の旅は、和山牧水歌集からの出発であった。何気なく開いた頁の
●恵那ぐもり 寒けきあさを 網はりて 待てば囮のさやか音になく
●恵那ぐもり 綱はりて待つ松原の いろの濃みどりけさは寒けき
の二首に心引かれ、酒と放浪の詩人牧水に憧れ、その足跡を訪ねてみたくなったのが動機であった。
やがて地酒に酔い、踊りに刺激されて、どうしても鳥屋場へ行き、この目で小鳥狩りの魅力を確かめたいと心に決め、宿の主人に案内を依頼する。
「小鳥狩りは、日の出が勝負ですので、これから山へ登らねばなりませんよ。」と云われ、しばし、躊躇はしたが、誘惑には勝てず、早々に宴を切り上げ、ふらつく足をようやく踏みしめて山行きとなった。
道々提灯を持った宿の主人から鳥屋の説明やら、遊びの心得などを聞く。
「つぐみの大群が空を覆う程飛来すると、囮が懸命に呼びかける。やがて群が、リーダーに導かれて下りて来る。その一瞬のタイミングを計って鳥屋師が、甲斐絹の小旗の付いた竿を振る。その音が、鷹の羽音に似ているので本能的に下方へ逃げる。そこに綱があり、捕捉される…と云う手順ですが、その成功率は、五十%位で、人と鳥との正に熾烈な知恵合戦ですね。それから、どうか囮が激しく鳴き出したら絶対に動いたり音を立てたりしない様にして下さいよ。昔苗木のお殿様でも『ウルサイ!!』と鳥屋師に頭を叩かれたと云いますからね。」と懇々と注意をされる。
「小鳥狩りは山国の蛋白源の補給から始まった純粋な猟でしたが、次第に高度な技術が磨かれ、色々な工夫がこらされて、今では鵜飼いに匹敵する一つの遊びとなりました。」 「成る程」と相槌を打ちながら息を切らして山を登る。
「どの社会でも優秀なパートナーが必要ですが、この猟では何より囮が鍵を握り、人鳥一体とならなければ獲物は取れません。
先づ獲った鳥の中から囮に向いているのを選ぶ目、それを餌付ける方法、更に十月中旬から十一月中旬までの猟期間に合せて、ベストコンディションで鳴かせる為の、色々な秘策、長い経験と研究の末でも尚、何十羽の候補鳥の中から使用出来るのは、せいぜい一羽か二羽程度でしょう。昔は、名鳥一羽は絹織物一背負いと交換出来るとさえ云われましたからね。囮は正に芸術作品ですよ。」熱弁を聞きながらやっと鳥屋場に到着した。それは粗末な山小屋で、いかにも年輪を思わせる鳥屋師が一人、準備万端を終えて一服していた。
俗塵を離れた静寂の中に、じっと耳を澄ませ、火を見つめていると、幽玄に遊ぶ境地でもあり、又、戦を前にした戦士の心境もかくやと思われてくる。
チチ、チチ、とかすかに囮達がつぶやいているのが、嵐の前の静けさと緊迫感をあおる。「私は、この待つ間が好きですね。」と主人は云う。鳥屋師は、ブッキラボーに無言である。暫く時が流れる。
突然、外の囮が一勢に囀り出した。シンフォニーが終楽章に近づく様に次第に激しく、やがてここを先途とかまびすく、囀りあげる。
あの無表情な鳥屋師の顔が別人の様に激しく活きかえり、追い竿を握った拳が緊張で震える。
「今だ!!」思わず声が出てしまい、隣りの主人に睨まれる。旗竿が風を切り激しい音を立てる。驚いた鳥達は瞬時に姿を消す。と網を張った竹竿が大きく揺れている。「入ったぞ。」一言云って、鳥屋師は元の無表情な顔に戻り、綱から獲物をはずすべく戸外へ出て行く。
いつの間にか陽は山の端を昇り、周囲の紅葉が朝露に濡れて鮮やかに山々を飾る。山の人達は、あの一瞬の歓喜の為に、囮の世話に一年間営々と、休みない努力を払い続けている。そうした見えない苦労がたくさん根底にあって始めて今日の、面白さ味わえるのであろう。本来、報酬とか喜びとかは、そう云う前提の上にあるものだろう。
「小鳥狩りの句も、たくさん残されております。
松本たかし先生は、
●濃紅葉の 流れとぶなり 鳥屋障子
高浜虚子先生は、
●大空に 又わき出でし 小鳥かな
●主人自ら 小鳥焼きくれて 山河あり
と詠んでおられます。ずっと昔から続いて来た、この小鳥狩りと云う猟法が、文学や芸能となって多く残されていると云う事は、猟から昇華されて文化の域になったと私は思うのですが、いかがでしょうか。」主人は、そう云って酒を注いでくれた。
島屋師が、つぐみと、いくちをとって帰って来た。囲炉裏にかかった真黒な鍋の味噌汁にいくちを投げ込み、炉の火を吹きながら、つぐみを竹串に刺し灰に立てた。
牧水が飲んだ様に、私も一気に盃を傾けた。
遠い五十年も前の旅の思い出である。